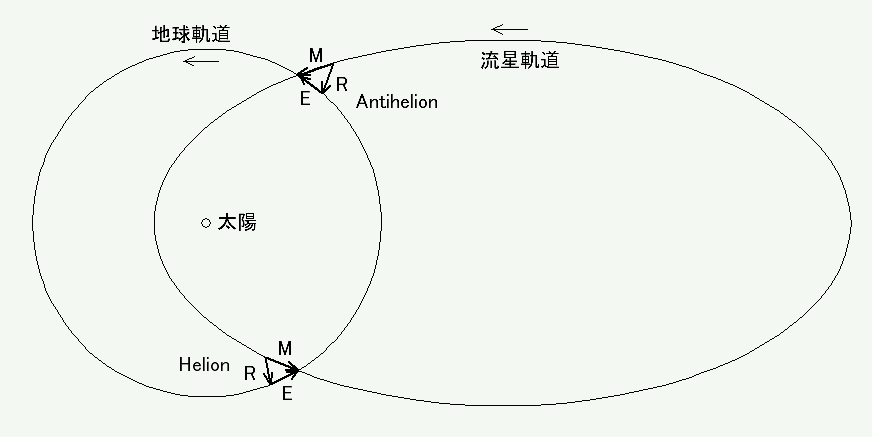
by 内山茂男
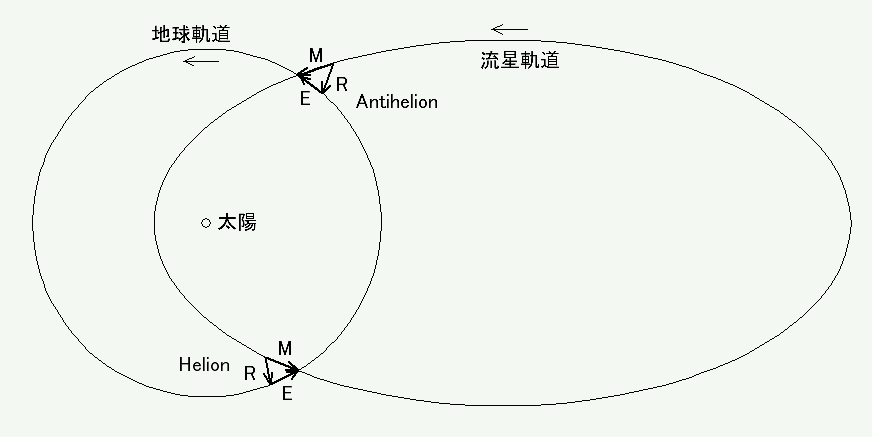 |
| 図1. 典型的な Antihelion の軌道 (輻射点は反太陽方向の15度東、対地速度は30km/s) |
| M: 流星物質の運動、 E: 地球の運動、 R: 相対速度。このRの始点方向が輻射点方向となる。 |
| アモール型 | : | 近日点が火星軌道の内側で、地球軌道の外側。 したがって、この軌道のままでは地球軌道と交差しない。 |
| アポロ 型 | : | 近日点が地球軌道の内側、遠日点が火星軌道の外側。 |
| アテン型 | : | 近日点が地球の内側、遠日点が地球軌道・火星軌道間。 |
図1の流星物質の軌道もこのアポロ型と同様なので、 Antihelion の母天体の多くはアポロ型小惑星と考えるのが素直な考えといえる。
これらの小惑星の中には、“もともとは彗星”であったものも少なからず含まれている可能性が高い。これらは、このように太陽に近づくのに公転周期が短いため、 かなり短期間で揮発成分は出尽くしてしまう。そうして残ったものは小惑星として観測されるようになるのである。 これらの“元彗星”がかなり以前にダストを放出し、このダストが Antihelion の流星になっているものも多いと思われる。
また、元彗星ではない岩石質の小惑星も、これに小天体が衝突すれば破片が飛び出して流星物質になるので、流星の母天体になる。
ほとんどのアポロ型小惑星は、地球軌道と交差しないので、その軌道のままでは地球と衝突せず、流星とならない。ただし、一般に、
惑星摂動による軌道進化により「軌道面の回転」が起きる。
これは、軌道傾斜角、近日点黄経は大きく変化せず、昇交点黄経と近日点引数が変化していくもの。
輻射点は太陽方向に対する黄経と黄緯を求める。
(軌道要素で使うのは、近日点距離 q 、離心率 e 、軌道傾斜角 i の3つだけ)
惑星による軌道進化は軌道面の回転だけではないので、一つ一つの小惑星からの流星輻射点としては、この計算方法は正しくない。 しかし、今回はアポロ型小惑星起源の流星輻射点の分布傾向を調べることを目的としている。すなわち、 流星物質の分布はアポロ型小惑星の分布とほぼ同様と考えて、アポロ型小惑星の軌道で流星物質の軌道を代用したということである。
上記の計算方法で各天体からの輻射点分布を求めて、マッピングしてみたのが下の図2である。
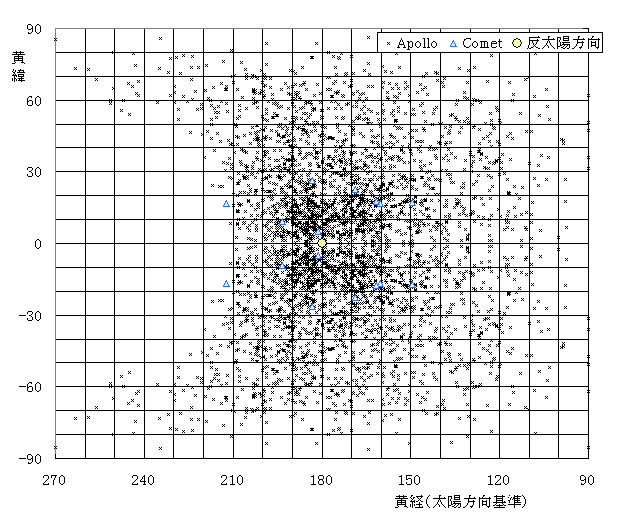 |
| 図2. 全輻射点 Map |
| ここでは、黄経0度を太陽方向としてしている。 したがって、反太陽方向は“黄経180度、黄緯0度”となる。 |
Antihelion sourceは、反太陽方向より東15度(この図で黄経195度)程度を中心とし(Arlt & Rendtel, 2006)、 黄経方向30度・黄緯方向15度程度の広がりを持つ(Rendtel, 2006) ということだが、図2を見ると、輻射点はもっとずっと広い範囲に分布し、 その密度のやや高いところは反太陽方向となっている。
目立つのは、黄経210度以上での空白領域である。これは、この空白域を輻射点とするためには、逆行軌道が必要となるが、 アポロ型小惑星と木星族彗星は全て順行軌道であるためである。
なお、今回の算出方法では、降交点での輻射点が黄緯プラス側、昇交点での輻射点が黄緯マイナス側となり、 対称的に分布する。
輻射点は図2の通り広く分布していたが、どのような軌道だと輻射点がどのあたりに分布するのかを調べてみた。
最初に、軌道傾斜角別に分けてみたのが、図3である。
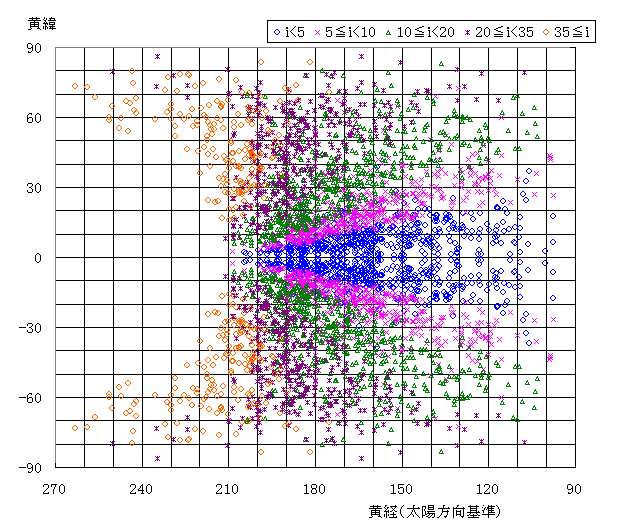 |
| 図3. 軌道傾斜角 i と輻射点分布 |
あたりまえだが、軌道傾斜角の小さいものは、輻射点が黄道に近い(黄緯が小さい)。したがって、Antihelion source の流星となっているものは、 軌道傾斜角が小さいものと言える。
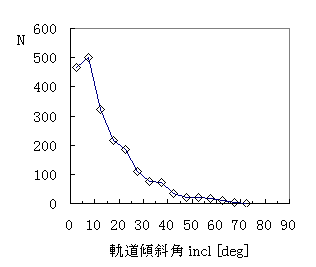 |
| 図4. 軌道傾斜角 i と小惑星数 |
軌道傾斜角と小惑星数の関係を調べると、図4のように、軌道傾斜角の小さいものが多い。このため、黄道付近に輻射点がやや多くなっている。
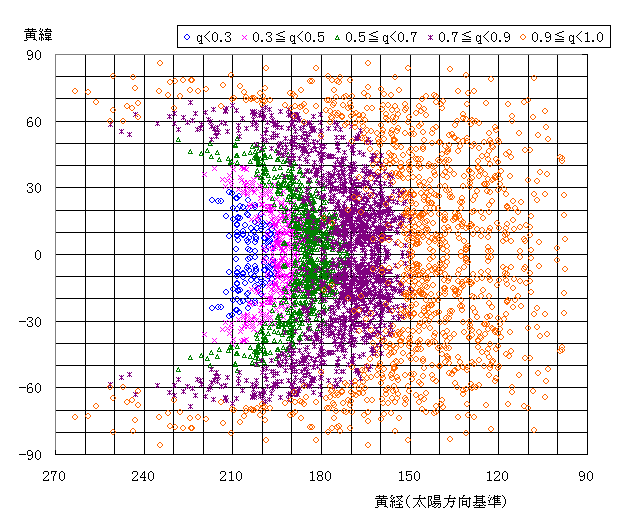 |
| 図5. 近日点距離 q と輻射点分布 |
近日点距離別に輻射点分布をマッピングしてみたところ、きれいに分かれた。 Antihelion source の“反太陽方向の東15度を中心とし、 黄経30度程度”という条件を考えると、近日点距離の小さいもの(近日点距離 q が0.6以下)が、 Antihelion source の流星になっていることになる。
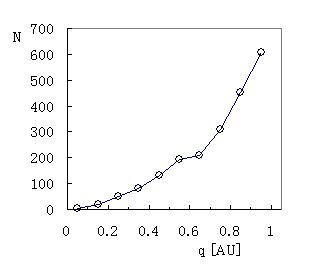 |
| 図6. 近日点距離 q と小惑星数 |
ところが、近日点距離と小惑星数の関係を調べると、図6のように、近日点距離の小さいものは少ない。 すなわち、 Antihelion source となるものが少ないのである。
なお、離心率 e と輻射点分布の関係も調べてみた。すると、 離心率の大きい(1AU に近い)ものが図の東側(左側)に多くなったが、近日点距離ほどきれいに分布が分離しなかった。 もともと近日点距離が小さいものは離心率が大きいものが多いという相関関係があるが、そのうち重要なのは近日点距離の方である。
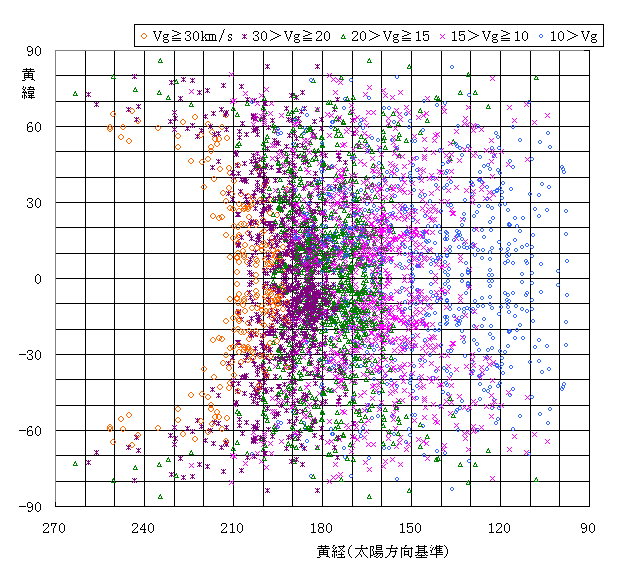 |
| 図7. 対地速度 Vg と輻射点分布 |
軌道傾斜角や近日点距離ほど輻射点分布がきれいに分離していないが、、全体的に東側(左側・近日点距離が小さいもの)は対地速度が大きく、 西側(右側・近日点距離が 1AU に近いもの)は対地速度が小さい傾向が見られる。すなわち、 Antihelion source の流星は、 対地速度が大きいものだということになる。
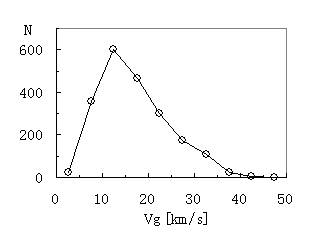 |
| 図8. 対地速度 Vg と小惑星数 |
対地速度 Vg と小惑星数を調べると、図8のように、10〜15km/s がピークとなっている。この速度は、流星としてはかなり遅いものである。 また、Antihelion source となると思われる速いものは少ない。また、全てが順行軌道であるため、 しし座流星群(逆行軌道)のような高速衝突になるものは存在しない。
対地速度Vgとは流星物質と地球が衝突するときの公転速度の相対速度で、地球の引力による加速は入っていない。 地球の引力による加速を考慮した速度V∞の場合、11.2km/s を下回ることはない。
これまで、どの小惑星でも輻射点を2つ(降交点と昇交点)ずつ求めて、マッピングしてきた。しかし、流星として観測できる確率は次のように同じではない。
上記2つの効果を考慮して、各軌道の流星出現確率を算出し、各小惑星毎に発生させた乱数(関数 RAND() )
の値より出現確率の方が大きい場合に輻射点がマッピングされるようにしたのが、次の図9である。
降交点と昇交点で別々の乱数を使用しているので、今回は黄道をはさんで完全に対称的にはなっていない。
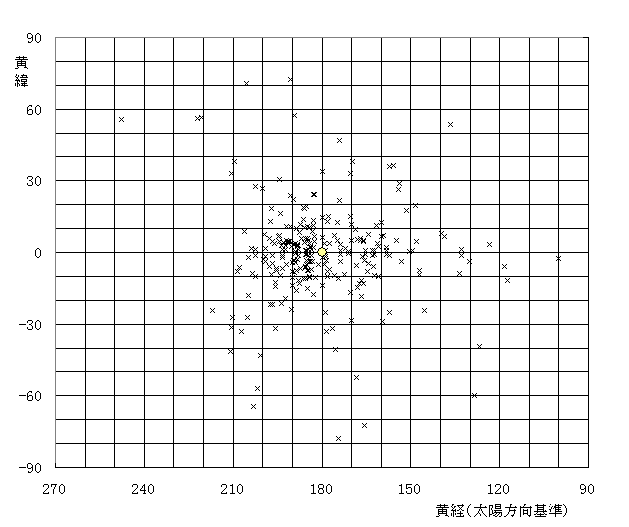 |
| 図9. 流星出現確率を考慮した輻射点分布例 |
出現確率を考慮すると、軌道傾斜角の効果で黄道から離れた領域からの流星が減少し、対地速度の効果で西側(図の右側)からの流星が減少する。
その結果、輻射点は広がっているが、 この図で黄経190度の黄道を中心とした領域に輻射点の集中が見られ、
Antihelion source の輻射点集中をほぼ再現できた。
また、“元彗星”の場合、近日点距離 q が小さい方が流星物質を多く放出した可能性が高いので、
それを考慮するともう少し黄経210度に近い方に流星の輻射点が増加すると思われ、観測されている Antihelion source にだいたい合うことになる。
このように Antihelion source は、多くの小惑星を母天体とする流星体の複合の結果であると考えられる。したがって、 「流星群」とするよりも「散在流星の多い方向」とする考えに賛成できる。ただし、中には、 1つの母天体からある程度の流星を出現させる「流星群」が隠れている可能性は否定できない。これを調べるには、TV 多点観測によるデータを積み重ねて、 じっくりと調査する必要があるであろう。
これは、第115回流星物理セミナー(2007年2月)で発表したものを、HP用に少し書き直したものです。